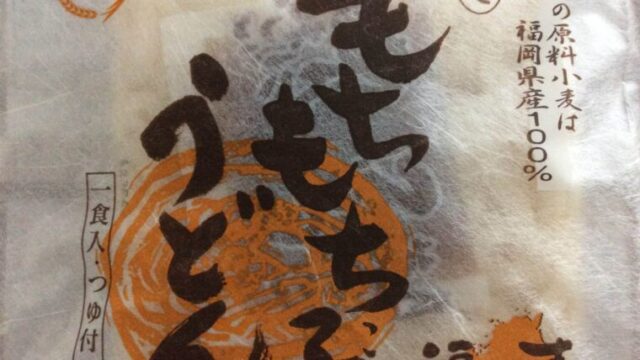お餅、買っていますか?それともつくっていますか?
一年を通していつでも食べたい餅好きの方は、ふだんから買い置きしていたり、餅つき機やホームベーカリーを使ったり、餅は常備食でしょう。
私は美味しいもち米を見つけてから自分で作るようになりました。餅つき機は大量に作るときに使い、普段使いはホームベーカリーです。
作り方や味にも違いがありますので、餅つき機とホームベーカリーの違いをご説明しますね。
また九州産の無農薬もち米もご紹介しますので、すでに餅つき機・ホームベーカリーを使っている方も、「餅は餅屋」派の方も、どうぞご賞味ください。
 杵つき餅と機械でつく餅に違いはあるか
杵つき餅と機械でつく餅に違いはあるか

「杵つき餅は美味しい!」というのが定説です。
郷愁が杵つき餅をより美味しく感じさせるという心理的なものもありますが、餅のつき方による餅生地の違いについては、物理的にも確かめられています。
臼と杵でつく方法を機械化したスタンプ式餅つきとミキサー式餅つきの二つの製法を比較した研究によれば、餅生地の組織細胞の違いは次のとおりです。
【参考文献:餅に関する食品学的研究】
・スタンプ式・・・残存米粒が多く粒径も大きい
・ミキサー式・・・糯米粒が細かく破壊され残存米粒の粒径が小さい
また、ミキサー式は、スタンプ式に比べて米粒細胞から流出した澱粉ペースト・気泡の量が多いこともわかっています。
スタンプ式つまり杵つきは、つくことによって空気が押し出されるため、気泡が小さく少なくなるのですね。
杵つき餅がのびやかでコシがあるといわれ、ミキサー式が煮崩れしやすい理由がわかります。
できることなら昔のように杵と臼で餅つきがしたいものです。ただし、杵と臼があっても上手につかないと良い餅はできません。
蒸したもち米が冷えないうちに手際よくつき上げなければ、でんぷんが老化して硬くなってしまいます。
お餅屋さんのように安定した杵つき餅を作る大変さは、子ども時代の経験からもよくわかるところです。ましてや杵もなし臼もなし人手もなしの現代の都市生活。
そこで、もうずいぶん前に電動餅つき機ブームが到来し、今は小型で少人数向きのホームベーカリーにも餅つき機能がついています。
餅つき機・ホームベーカリーの長所は、材料を入れてボタンを押すだけ、誰が作っても安定した餅ができるという点です。
さらに、餅としての味わいで言えば、確かにつきたては杵つき餅のコシに負けると思いますが、冷えてしまえば同じ餅!美味しいです。
 簡単便利な餅つき機・ホームベーカリーの違い
簡単便利な餅つき機・ホームベーカリーの違い

さて、今度は餅つき機・ホームベーカリーの餅つき機能を比較してみましょう。2合のもち米を使った場合の一般的な手順です。
| 項目 | 餅つき機 | ホームベーカリー |
| 材料 | もち米・水 | もち米・水 |
| 下準備 | ・もち米を洗う ・洗ったもち米を水に浸す (6時間~8時間) ・ザルにあげて10分ほど水を切る | ・もち米を洗う ・30分ほど水を切る |
| 工程 | ・容器にもち米を入れる ①蒸す ②こねる ・30分ほどで出来上がり | ・容器にもち米を入れ 餅つきメニューを選びボタンを押す ・1時間ほどで出来上がり |
大きな違いは次の3点です。
・餅つき機は浸水時間が必要だが、ホームベーカリーは不要
・餅つき機は餅つきにかかる時間がホームベーカリーの半分
・餅つき機は餅を蒸してからこねるが、ホームベーカリーは蒸す工程がない
より杵つき餅に近いのは餅つき機ですね。ホームベーカリーは「焼く」のが本領ですので、もち米も熱を加えてこねます。
蒸すという工程が入るのとはいらないのとでは、餅の食感が違います。ホームベーカリーで作ると柔らかめになりがちです。
また、餅つき機は一度にたくさん作れますし、蒸す水分量も調節できます。
このように、機械で作る餅は、餅つきに特化した機能をもつ餅つき機のほうが優位です。
しかし、ホームベーカリーでも餅がつけるという多機能性が捨てがたいのは事実。柔らかめのお餅が好きな方、煮崩れしたお雑煮が好きな方にはホームベーカリー餅、おすすめです。
私も「煮崩れ志向」ですので、食べたいときに食べる分だけすぐにできるホームベーカリーはありがたい存在です。
 ホームベーカリー餅は美味しくないの?美味しい餅を作るコツ
ホームベーカリー餅は美味しくないの?美味しい餅を作るコツ
蒸さないホームベーカリーの餅は、作り方にコツがあります。
このコツさえつかめば、ホームベーカリーであっという間に美味しい餅の完成です。
コツは水加減だよ♪♪
たとえば、シロカのホームベーカリーレシピでは、もち米250gに対して水が210㎖となっています。
作り方はとてもカンタンです。
もち米をといでザルにあげて30分間水を切ったあと、もち米と水をパンケースに入れてボタンを押すだけ。
1時間15分で、つきたての餅の出来上がりです。
しかし、いざ餅を取り出すとき、こんなはずじゃなかった!!!ということも。
餅が柔らかすぎてべろんべろん。
おじゃる丸の貧ちゃんのような(わかりにくい)形状になってしまう原因は水加減です。
分量を守ったのに水加減を失敗する原因は2つあります。
〇もち米の水切りが不十分
〇もち米そのもの
同じように作ったつもりでも、水切りができていなかったり、もち米の種類が違ったりすると、うまくいかないことがあります。
お好みの硬さの餅ができるまで、水加減を調整してみましょう。
 もち米なら「ひよくもち」!
もち米なら「ひよくもち」!
もち米の成分
もち米もうるち米も主成分はデンプン。アミロースとアミロペクチンという成分です。
もち米とうるち米の違いは、このデンプンの構成にあります。
うるち米は、アミロースが2割、アミロペクチンが8割。もち米は、ほぼ全てアミロペクチンです。
アミロペクチンは炊くと粘りが出ます。冷めてもおいしいと評判の低アミロース米は、アミロペクチンの含有量が多いお米です。
日本のうるち米に比べて、例えばタイ米などのインディカ種の長粒種はアミロースが多いのでパサパサした食感になります。カレーやピラフに向いていますよね。
対してもち米のデンプンはアミロースではなく、アミロペクチンだけですので、あのもっちりモチモチ感が出るわけです。
九州のもち米といえば「ひよくもち」
九州の直売所でお餅を買うと、「ひよくもち」と表記してあることが多いです。
もち米といえば佐賀県産のイメージがあります。もち米イコール佐賀イコール間違いない!と思って買います。
ひよくもちは1971年に福岡で育成され、主に九州で生産されています。「ひよく」は九州の「肥沃」な土地から来ているネーミングです。
筑後川沿岸に広がる筑紫平野(つくしへいや)一帯は正に肥沃な農業地帯。なかでも佐賀平野と呼ばれる地域は日本有数の米どころです。
また、西日本一の米の収量を誇る熊本もひよくもちの産地。
私は福岡県の道の駅くるめで農薬・化学肥料不使用のもち米を購入しています。とろけるように美味しいお餅ができます。

耳納連山のふもとで育ったきれいなお米です。そのうえ真空パックで丁寧に梱包され、価格は一升(約1.5Kg)800円!
備蓄用に買ったのですが、誘惑に負け次々に封を切ってしまいました。残念ながら通販では取り扱いがありません。
通販で買うことができる「無農薬」の九州産ヒヨクモチの購入先を、佐賀・福岡・熊本からご紹介します。
〇佐賀県 特別栽培もち米「ひよくもち」 農薬・化学肥料不使用!
〇福岡県産 ひよくもち 筑後久保農園 自然栽培米 餅つき機・ホームベーカリーでいつでも餅つき
餅つき機・ホームベーカリーでいつでも餅つき

昭和の昔の杵つき餅を思い出しながら、餅つき機・ホームベーカリーで手軽にお餅を作りましょう。
杵つき餅により近いお餅を求めるなら餅つき機、柔らかめのお餅がお好みならホームベーカリーが便利です。
気に入ったもち米が選べる手づくりのメリットを生かして、「無農薬」のもち米でお餅を作ってみてはいかがでしょうか。
九州産の「無農薬」ひよくもちもおすすめです。
餅は腹持ちも日持ちもよい最適な備蓄食料。冷凍しておけばカビることもありません。
玄米は備蓄してももち米までは気が回らないものです。機を逃さず、ぜひとももち米も備蓄しておきましょう。
九州産玄米についてはこちらの記事でもご紹介しています。
【関連記事:備蓄用の玄米に九州産を選ぶ理由は?こだわりの玄米3選もご紹介!】